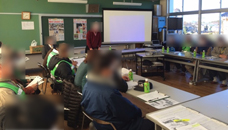交通事故に遭い24時間以内に亡くなった人は2022年は2610人で、6年連続で戦後最少を更新しました。交通事故件数も30万件余りと、最多だった2004年の3分の1以下でした。環境(environment)、工学(engineering)、規制・強制(enforcement)、教育(education)の「4E対策」の効果の影響とみられます。しかし、歩行中の子どもが被害者となる痛ましい事故は相次いでおり、日本損害保険協会では、一般財団法人日本自動車研究所(茨城県つくば市)が取り組んでいる交通安全教育や周囲の監視(見守り)活動に関する研究を支援しています。子どもの事故被害低減について同研究所自動走行研究部の大谷亮主任研究員に、お話を伺いました。

交通事故による死者は自動車乗車中より歩行中が多く、年齢別では人口10万人当たりの死傷者数は7歳児が最も多くなっています。それまで保護者と一緒だった子どもが小学生になり一人で登下校するようになることや、まだ幼くさまざまな交通環境に適応できないことなどが要因とみられます。集団登下校中の事故が相次いで発生し社会問題となっていたので、私が専門とする心理学の観点から子どもの事故を減らしたいという思いが、研究を始めたきっかけの一つです。
また、先進運転支援システムや自動運転などの有益なシステムを適正に利用するには、安全運転を心がけるドライバーの「安全態度」が重要となりますが、大人になってから態度を変えるのは困難です。そこで、将来のドライバー候補である子どもたちを、小さいときから育成し安全態度を育みたいという思いもありました。
内閣府の中央交通安全対策会議が2021年にまとめた第11次交通安全基本計画には、「重視すべき視点」として高齢者と子どもの安全確保が最初に挙げられています。2019年度から3年間、損保協会の助成を受け、面談やアンケートによる調査、研究を継続できたことに感謝しています。

子ども自身が交通安全や他者への配慮に関する能力や技能を身につける教育が必要ですが、発達特性を考慮しないと効果的・効率的ではありません。俯瞰(ふかん)図や人形、おもちゃの車を使った交通安全教育の際、年齢差が出るのが、図のある位置から遮蔽(しゃへい)物の陰になっている車が見えるか見えないかを尋ねたときです。1年生には「見える」と答える傾向が高く見られました。実際と俯瞰的な見え方の違いを理解できないからであり、4年生や6年生にはない特徴です。また、自分が交通事故に遭う可能性があるかどうかについても「自分は遭わない」という回答は1年生に多く見られました。交通事故のリスクという抽象的な概念が分からず、事故に遭ったり目撃したりした経験も少ないからでしょう。こうした特性を考慮して、俯瞰図だけでなく実際の場面を想定した子どもの視点での映像を見せるといった工夫が必要になります。
年度・世代差もあります。道を横切るときに横断歩道を渡るという知識の有無は、同じ1年生でも今年、昨年、一昨年で違います。保護者や学校、地域で交通安全教育を行ったかどうかが効いていると予想されます。年齢的に苦手な部分もあれば、教えれば分かる部分もあるということです。交通事故は「運が悪かったから起こる」と答える児童は、どの学年にもいました。そういう子どもは交通安全を勉強しても仕方ないと考えてしまうので、運ではなく自分の行動が事故につながることを分かってもらわないといけません。

子どもを対象にした安全教育を実際に行っています。道路を横断するときは「安全な場所を探し、立ち止まって、右と左を見て安全を確認し、手を上げて…」と教えますが、小さい子どもは頭を左右に振る表面的なまねにとどまり、確認が抜けてしまいがちです。
そこで私も委員として参加した京都府警の検討会で2021年、手を真上に上げるのではなく手のひらを車に向ける方法を考案しました。左右の安全確認とドライバーへの合図という二つの作業を、一つの動作で行えます。2022年にはNHKと一緒に、安全な横断歩道の渡り方のポイントを盛り込んだ「ててて!とまって!」という歌をつくり「みんなのうた」で放映されました。
これらはプロトタイプのようなもので、子どもや地域に合ったオーダーメード教育ができるのは保護者、学校、地域のボランティアです。また、独力で安全を確保できない子どもは、事故に遭わないよう、周囲の大人が見守らなければなりません。安全教育や見守りは、保護者にとっては子育ての一部、地域では防犯、防災と並ぶ活動の一つと位置付けることが重要と考えています。