「高次脳機能障害」は、交通事故や転倒による脳外傷、くも膜下出血、脳腫瘍などの後に起こる認知機能の低下や人格変化の総称です。患者には自宅での生活や就労などの社会参加に向け、治療や生活支援が欠かせませんが、中でもリハビリは試行錯誤状態です。神奈川工科大と神奈川リハビリテーション病院は、リハビリの一手法としてグループ訓練を体系化し、地域の障害者福祉事業所などで実践できるよう「高次脳機能障害がある方へのグループ訓練(手引き)」を作成しました。日本損害保険協会はこの活動を支援しています。手引きの内容や狙いについて、神奈川工科大の小川喜道名誉教授、神奈川リハビリテーション病院の青木重陽医長、瀧澤学総合相談室長(メディカル・ソーシャルワーカー)にお話を伺いました。
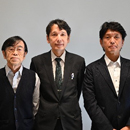
高次脳機能障害の患者は国内に30万~50万人、あるいは10万人当たり約50人と言われています。症状は、記憶、集中力、遂行機能などの障害のほか、余計なひと言を言ったり、怒りっぽくなって、時に暴言、暴力に至ったりすることもある社会的行動障害などです。症状には損傷部位や受傷前の状況、元の性格、患者の過ごしている環境など多くの因子が関係し、相互に作用し合うため〝百人百様〟です。一つの症状に一つの治療・リハビリを当てはめる手法では歯が立たず、リハビリを検討する上での障壁となっています。
そこで、症状ごとではなく包括的、全人的に対応して全体的な機能を上げようと、通院患者を対象にした「グループ訓練」というリハビリが1980年代に米国で始まり、世界に広まりました。日本には診断基準ができた2000年代に入ってきましたが、費用も労力もかかるため、今でもやっている施設はわずかです。最近は、患者が自分の障害を認識する「気づき」に焦点を当て、自分の状態と行動をコントロールする能力を付ける形へと発展しています。

リハビリの最終的な目標は患者の社会参加、就労で、グループ訓練は入院リハビリから通院リハビリに移行した患者が社会参加するための準備としてやっています。手法は「人のふり見て、わがふり直せ」です。患者は自分が症状を持っていることに気づけないでいます。そこで、同じような立場の人と接したり一緒に作業したりすることで、自分への理解を深めるわけです。
具体的には、6人程度のグループで、まず座学で症状や対応方法について勉強してもらいます。そして片足立ちで体のバランスや柔軟性を経験し、それを他の患者と比較するなどして、自分の状態を認識してもらいます。スマホを使ってルートを調べ、旅行の計画を作ったりもします。以前の自分と違うので、社会に出たらうまくいかないこともあることを実感してもらい「こんなことも起きる。その時は相談においで」と、事前に〝種まき〟とも言える情報提供もしています。週2回、4カ月のプログラムで、スタッフ20人が関わることもあって、年間12人が限度です。

各地の支援コーディネーターは事例検討や研修、家族会などを通じ、試行錯誤しながらリハビリを頑張っていますが、もう一歩踏み込んだものが必要と考えていました。手引きは、海外から持ち帰った情報をベースに、20年積み重ねた経験を専門分野ごとに再構築し、グループ訓練のエッセンスをまとめました。患者が安定して過ごせるノウハウや、支援計画を立てる際の事例も書いてあります。手引きは音声と字幕をつけたDVDとともに、各地の家族会、障害者福祉事業所、利用者を高次脳機能障害に特化した施設、支援拠点機関など約200カ所に送付しています。自分たちなりに工夫するきっかけにしてもらい、地域に浸透することを願っています。
高次脳機能障害への施策は、障害者総合支援法の地域生活支援事業都道府県実施分である「高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及事業」として、全国ほぼ一律に展開されていますが、予算や規模は自治体によって格差があると感じています。このため高次脳機能障害支援法の制定が悲願です。当事者、家族、支援者のサポート態勢を構築するという理念を持ち続けることが大事だと考えています。

